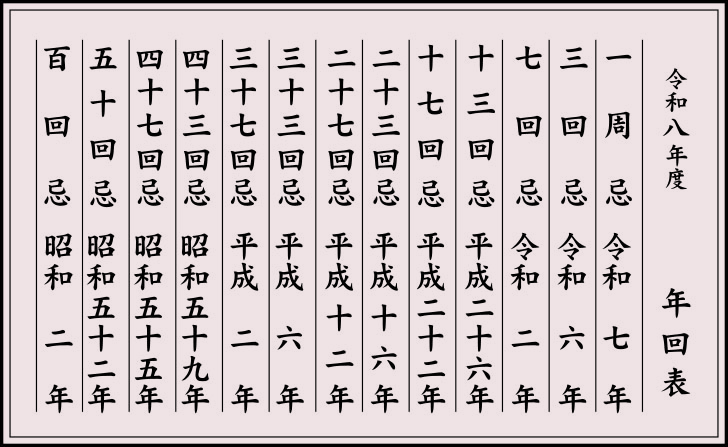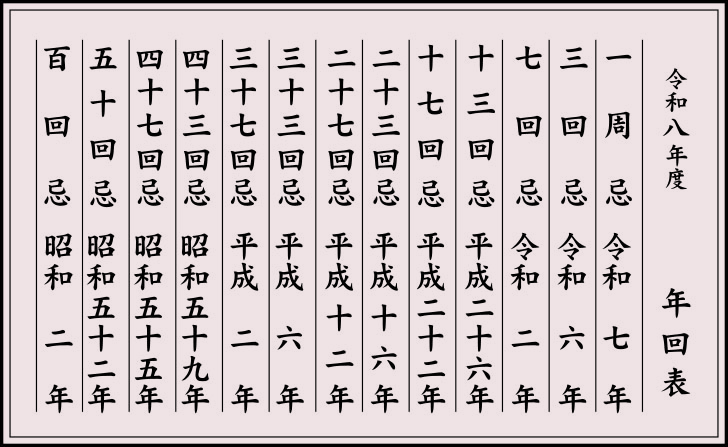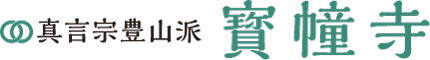寳幢寺について
縁 起
寳幢寺は弘法大師開宗の真言宗豊山派の寺院です。
大同元年(806年)、宥恵法印の開基とされ、
山号を補陀洛山、院号を観音院、
寺号を寳幢寺と称します。
元々、近隣に所在した末寺の七つの寺院
(阿弥陀寺、龍性寺、正円寺、福寿院、延命寺、
東医寺、聖光寺)が
明治五年の
「無檀・無住寺院の廃止令」の通達により、
本寺の寳幢寺に合併され、
現在の地(旧阿弥陀寺の境内)に
移築されたものです。
ご本尊様は「聖観世音菩薩」で、
その他に「阿弥陀如来立像」と「大日如来坐像」
が市の文化財に指定されています。
木造阿弥陀如来立像
「阿弥陀如来立像」は、
治承三年(1179年)千葉常胤が海中から
二体の「阿弥陀如来像」 を得た後、
大須賀原に仮屋を建てて安置し、
後に文治二年(1186年)阿弥陀寺の
本尊としたと伝えられております。
阿弥陀寺が明治の初めに 廃寺となりましたので、
当山に移されたものです。
この「阿弥陀如来」は小さい仏像でありますが、
相好円満で中世の佳作とされております。

(法量) *像高 45.1
参考文献:「千葉市の仏像」 平成四年発行 千葉市教育委員会 社会教育部文化課
木造大日如来坐像
堂ノ山の境外仏堂から遷した
「大日如来坐像」は、
蓮台の上に鎮座し、高さ百二十センチメートル、
漆箔の座像で、玉眼を入れ、
金銅透彫の宝冠を戴いております。
また、胸には金剛界大日如来の印である
智拳印を結び、眉目秀麗、
体幅堂々として気品があり、
生気を失わない衣の襞の線は実に規則的に
美しい曲線を描いております。
快慶の流れをくむ
室町時代の優作と言われております。

(法量)
*像高 120.5 *髪際高 88.0 *面長 22.3
*頂~顎 55.1
*面幅 25.0 *耳張 27.3
*耳朶張
23.4 *面奥 28.5
*胸厚(右) 30.3
*腹厚
37.5 *肘張 55.5 *膝張 88.2
*膝高(左) 16.5 *同(右) 17.0 *膝奥 70.5
*裳先奥 80.0 *台座高 42.4
参考文献:「千葉市の仏像」 平成四年発行 千葉市教育委員会 社会教育部文化課
年中行事
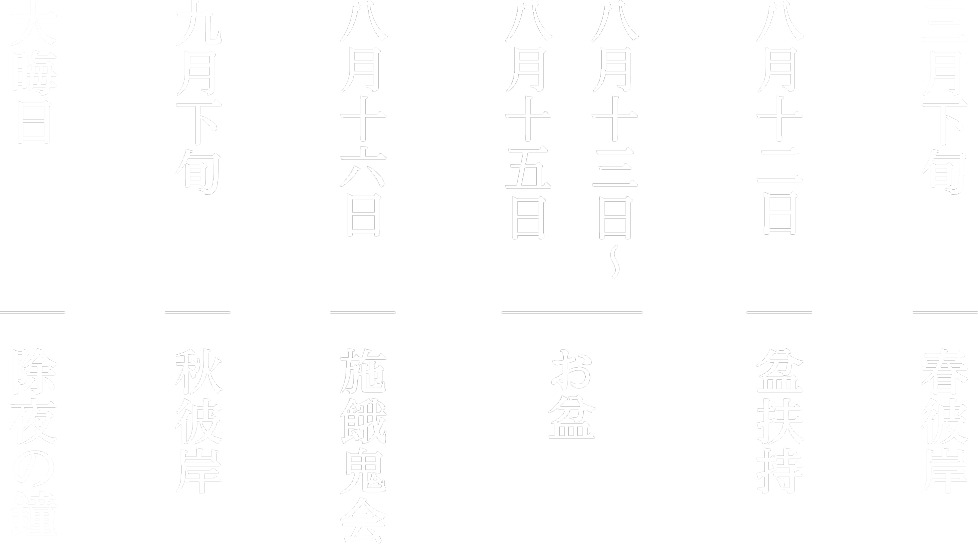
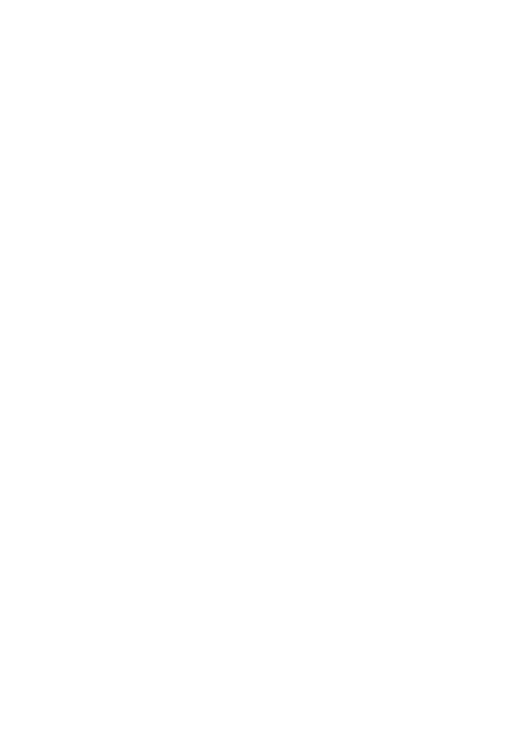
年回表